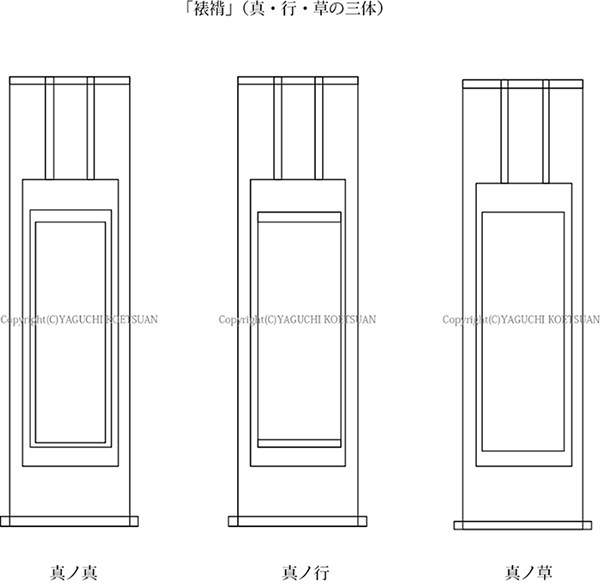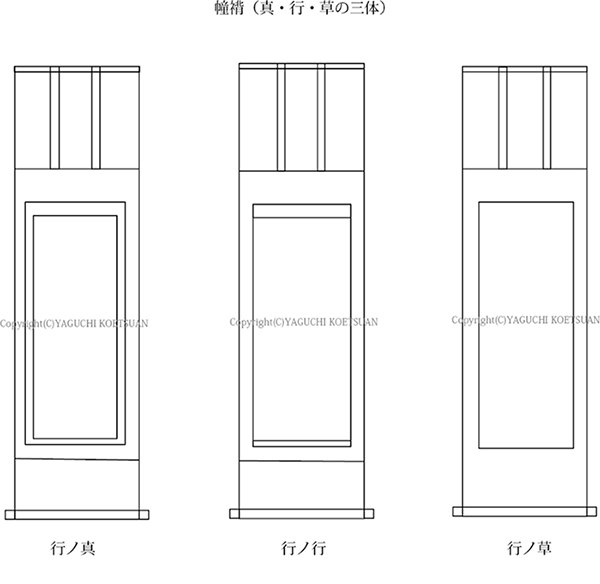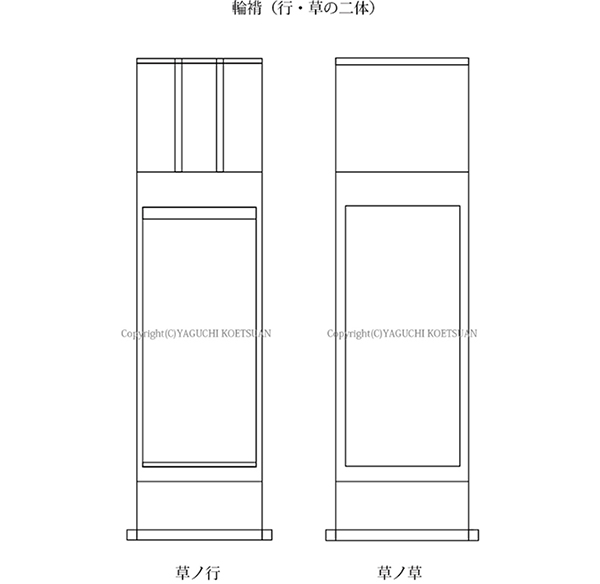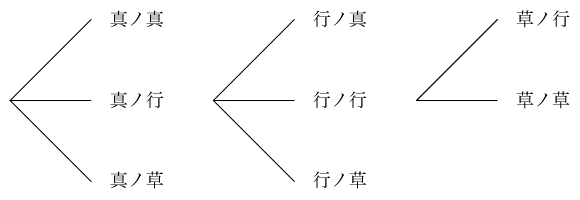表具の歴史は古く、仏教と深い繋がりがあります。我が国における表具は仏教の伝来と共にもたらされた中国の隨・唐の経巻や仏像画などの擬製に端を発するとされています。
現在の掛け軸の式は支那の法の伝来によるもので、鎌倉時代支那の禅僧の請来した掛物を擬製したものに始まります。我が国最古の法律書である『令』の、「職員令中務省図画寮」の中に「校寫装潢」とあり、その義解に「義治曰装染色曰潢」とあります。潢とは染めることで、古来より経巻類に使用する料紙は防虫効果がある黄檗(きはだ)で染めていました。この時代に活躍したのが経巻の仕立てを専門に行う経師です。ここではまだ表具師(表背師、表補衣師、裱褙師)は登場しません。
表具の名目(表具師)が文献に登場するのは、桃山時代以降となります。その一例として、大正11年に発行された山本元著の『表具のしをり』では、神谷宗堪筆の「長闍堂記」や古今の狂歌1050首「古今夷曲集(十巻四冊)」などをあげています。また、建保二(1214)年の東北院職人歌合及足利時代の書である七十一番歌合中の三十二番職人歌合九番に「ひょうほうゑ」の名称が次のように伺えます。
『山水もはるそ見事のへうほうゑ、花の錦をちうべりにして』とあり、その判に『此山水の絵、象牙の軸、金襴の表紙よりも、はなの錦の中べりうつくしくしたてられて、山水の春景も光そふ心地し侍るに』とあります。
ここでは「錦の中べり」とあり、つまりは中廻しに使用された錦は山水の絵と見事に調和し絵画そのものを引き立てていることを表現しています。
このような文献から、絵画や墨蹟を引き立たせるために、表具を施すという文化が鎌倉時代から一般庶民にも広がってきたという事が伺えます。
掛け軸が大きな転機を迎えたのは利休の時代です。かの利休は、「茶の湯の掛物は幅の広さは富貴であるとして、一尺二、三寸となり、大文字のは二行あらば見下して又見上げるるがあしとして一行物がはやり、表具も光輝くは尊いきとして、皆紙表具、或は黄絹」とし、茶掛けの概念が誕生しました。
茶掛けでは、閑寂の風趣である侘び・寂びを第一に考え、表装も華やかなものでなく落ち着いたもの、第二に季節感が顕著に感じれること。そして第三に、禅の心に通じるものを持つこと(捕らわれない心の自由さ)。最後に伝来が明かなことが茶掛けたることの条件とされています。
このように掛け軸の歴史は古く、紙や絵絹に描かれた絵画や墨蹟を「仕立てる」ということは、そのものの本質を理解しまた後世に伝えるといことでもあります。
その一例として、古来より『御物』といわれる掛け軸には、名物裂が使用され、高価な軸先、そして著名人による書付や箱書きがされ、大切に現在まで伝わっています。